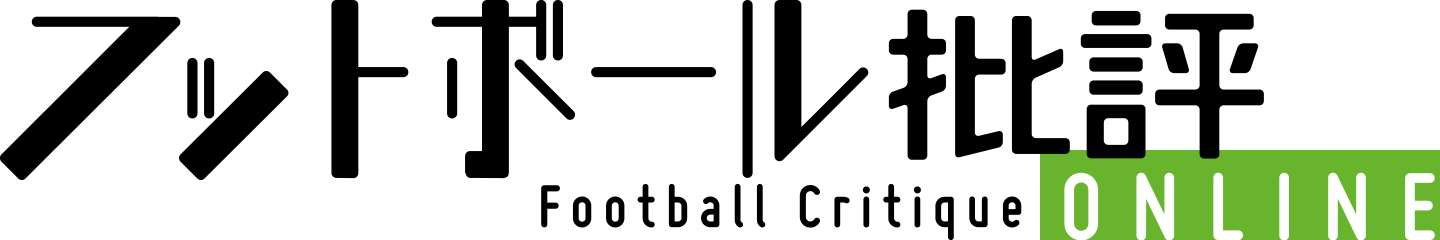フットボール批評オンライン 無料公開記事
小社主催の「サッカー本大賞」では、4名の選考委員がその年に発売されたサッカー関連書(漫画をのぞく)を対象に受賞作品を選定。選考委員の一人でもあるフランス文化研究者、作家、文芸批評家の陣野俊史氏にサッカーにまつわるあれやこれやに思いを巡らせてもらう連載「ゲームの外側」第5回は、生まれ育った長崎のサッカーチームV・ファーレン長崎について。
(文:陣野俊史)
2024年のシーズンはV・ファーレンにとって、特別な節目の年だった

【写真:Getty Images】
私は長崎で生まれ育った。長崎市内である。
大学に入って東京に出て来るまでずっと長崎に住んでいた。いま、親が高齢になったこともあり、年に4~5回ほど長崎に帰る。
一度帰ると1週間弱いるので、じつに1年のうち1カ月近く、長崎で過ごしていることになる。想像もしなかった事態だが。
その長崎にサッカーチームができて、のみならず、J2でそこそこの地位にいる。V・ファーレン長崎のことだ。
正直に言えば、数回しかスタジアムで試合を観たことがない。それも1シーズンだけ昇格した、あの夢のようなJ1の時代がメインだ。
なかでもサンフレッチェ広島戦は特別な感慨があって、もちろん感慨だけではなく、被爆した都市同士の、平和を祈る試合も行われたと記憶する(特別のユニも買ったのだ)。
2024年のシーズンはV・ファーレンにとって、特別な節目の年だった。
長崎駅の近く、最高の立地に拠点となるホームPEACE STADIUMが完成し、盛大なこけら落としも行われた(福山雅治が無料ライヴをやったり、とか)。
だが、J1には届かなかった。自動昇格まで1ポイントだけ届かなかった。
4チームで争ったプレーオフでは、いきなりベガルタ仙台に完敗した。なんてこったい、と思った。
東京でやきもきしていた。試合を画面で見ているしかない自分が腹立たしかった。と同時に、ホームスタジアムのきらびやかさが、どうもしっくりこない感じだった。
もちろん、ホームのスタジアムは立派であるに越したことはない。だが、諫早市にあった元のホーム、トランスコスモススタジアム(略称トラスタ)が好きだった。
陸上のトラックが併設されている、まあ、よくあるスタジアム。
だが、試合が終わって陽が落ちたあと、サポーターのみんながJR諫早駅(いまは、新幹線が停まる駅に似つかわしく、立派な駅舎になっている)まで30分近くかけて歩いて帰る姿(もちろんそのほうが圧倒的多数)を見送りながら、トラスタから反対方向へ、つまり諫早の市街地とは逆方向にチャリで帰るのは、なんとも楽しかった。
一人だけ、群れから離れるのだ。
長崎市内で生まれ育ったのに、どうして諫早の、どちらかと言えば過疎化した地域にチャリを走らせていたのかというと、その先に親がいま暮らしている実家があるのだった(老母が諫早の郊外の、だだっぴろい家に住んでいる)。
あの、夏の暑さがいつまでも残るなか、駅とは逆方向に走る(そして汗だくになる)圧倒的なマイナー感覚が忘れられない。トラスタには愛着がある。
サポーターのみんなはどうなのだろう。
トラスタでの試合が終わり、新しいスタジアム(ピースタと呼ばれているみたいだ)での試合が始まるあたり、V・ファーレンサポーターは、トラスタには感謝を捧げ(感涙とともに)、ピースタにはこれからよろしう、と挨拶していた。
そうとしか書けないだろうし、私の立場からあれこれ言うこともない。立派な、サッカー専用のスタジアムなんてすごい。
昨シーズンの最終盤、勝ち続けていたV・ファーレンもすごかったのだ(しかし届かなかった……)。
ただ、私のなかでは、ピースタへの期待よりも、わずかだがトラスタへの愛惜が上回っていた。
お前は東京に住んでいるからそんなノスタルジーを感じているんだろう、前を向いて、そう、J1自動昇格を狙って、2025年は飛躍するのだ――という意気込みもめちゃくちゃわかる。
でもちょっとだけ、ほんの少しだけピースタにノリきれない自分がいたのだった。
2025年の正月。長崎市内に用があったので、諫早駅から長崎駅まで西九州新幹線に初めて乗った。
乗車時間9分。風情もへったくれもない。荷物を棚に上げる時間もないくらい、あっけなく長崎駅に到着する。
せっかくなので、路面電車(長崎電気軌道)で長崎市内の家に行くことに。電停の名前を少し書き連ねる……。「長崎駅前」で乗車、すぐに「八千代町」。
続いて「スタジアムシティ サウス」「スタジアムシティ ノース」……。え?
「宝町」は? 「銭座町」は? 消えた? 続けて「茂里町」「浦上駅前」、そして「大学病院前」……以下、従来どおり。
スタジアムの存在感がとにかくすごい。電停の名称変更が行われた、というのは噂で聞いていた。だが、ふたつも「サウス」と「ノース」ができているなんて、想定外だ。
私ははっきり面食らった。そもそもサウスで降りたほうがいいのか、ノースで降りたほうがいいのか、さっぱり。
ただ正月は試合をやっていない。シーズンはまだ先。
それでもピースタ界隈の賑わいは、電車の窓からでも十分に伝わってきた(私は結局、降りなかった)。
もちろんBリーグの長崎ヴェルカの拠点も併設されているから、というのもあるだろう。ピースタのピッチ上を滑空する「ジップライン」も人気があるらしい。
そもそも高いところが嫌いなのでジップラインに挑戦する道はなかったとは思うのだが。
隣接地に開業したホテルも、ピッチに臨む側の部屋が、長崎港を見下ろす、眺めのよい部屋よりも高い料金設定になっているなど、サッカーを観る環境は十分整っている。
というか、サッカーを観るという目的に特化した界隈の作り込みは、見事というしかない。
だがしかし、と故郷を離れて40年も経つ人間は思うのだが、「宝町」と「銭座町」は残しておいてほしかったな、と。
町の名前にまつわる甘酸っぱい感情や記憶がある。その名を聞いただけで、去来する複数のイメージは確実にある。
それがきれいさっぱり拭い去られたように感じられたことは確かだ。
それともうひとつ。
春にピースタで試合を観るという大学生たちにも言ったことだが、ピースタの向こう側を流れる川を「浦上川」といい、その川には、1945年8月9日の原爆投下のあと、水を求めて集まった夥しい人々が死んでいった場所なのだ、ということも、誰かが言わなければならないのだろう。
それらの歴史的事実は、長崎でサッカーをすることと、不可分のような気が、いまの私にはしている。
ひとまず、この春には必ずスタジアムで試合を観る。
(文:陣野俊史)
【関連記事】
ティエリ・アンリ フランス代表エスポワールの「監督」辞任に思うこと 【ゲームの外側 第1回】
彼女たちのサッカーが「ありのままに」存在しているからこそ、この小説は書かれた。『ひとでなし』書評【ゲームの外側 第2回】
「独立の立役者」大切なサッカー選手ラシッド・メクルーフィの訃報に触れて【ゲームの外側 第3回】
ワールドカップの勝敗だけでは、あの国アルジェリアのサッカー熱は計測できない『不屈の魂』書評【ゲームの外側 第4回】
第11回「サッカー本大賞2024」の授賞式が開催! 各受賞作品は?
陣野俊史(じんの・としふみ)
1961年生まれ、長崎県長崎市出身。フランス文化研究者、作家、文芸批評家。サッカーに関する著書に、『フットボール・エクスプロージョン!』(白水社)、『フットボール都市論』(青土社)、『サッカーと人種差別』(文春新書)、『ジダン研究』(カンゼン)、共訳書に『ジダン』(白水社)、『フーリガンの社会学』(文庫クセジュ)がある。その他のジャンルの著書に、『じゃがたら』『ヒップホップ・ジャパン』『渋さ知らズ』『フランス暴動』『ザ・ブルーハーツ』『テロルの伝説 桐山襲烈伝』『泥海』(以上、河出書房新社)、『戦争へ、文学へ』(集英社)、『魂の声をあげる 現代史としてのラップ・フランセ』(アプレミディ)など。
【了】