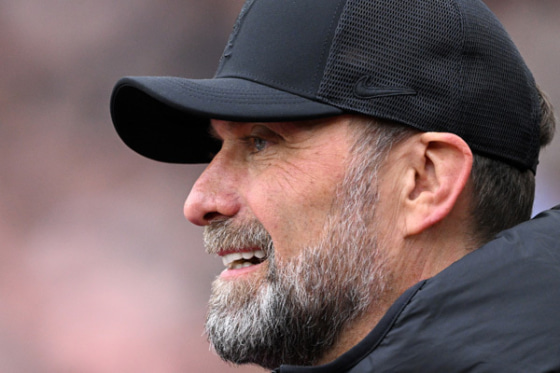フットボール批評オンライン 特集記事
ユルゲン・クロップという指揮者の下で奏でられたリバプールのヘビーメタルは、9年の間に少しずつ音色を変えていった。『“総力戦”時代の覇者 リバプールのすべて』の著者・結城康平が、戦術的な視点からクロップ政権下のリバプールを史実として詳細に記す。(文:結城康平/本文19,456字)
※全文を読むためには、記事の購入が必要となります。
リバプールが奏でたヘビーメタルの音色
ボルシア・ドルトムントで若く勇敢なチームを率い、リスクを厭わないハイプレスで相手の自由を奪う。ユルゲン・クロップは多くの若手指揮官を輩出するドイツで新世代のコーチを牽引する存在となり、イングランドの名門に招聘された。ドルトムント時代のコメントが、彼のフットボール哲学をシンプルに要約している。フランスの名伯楽としてアーセナルで長期政権を築いたアーセン・ヴェンゲルのフットボールとの違いを問われ、彼は次のように答えた。
「アーセン・ヴェンゲルはボールを保持することを好み、丁寧にパスしながらフットボールをプレーするスタイルだ。しかし、それは静かな曲だろう。まるでオーケストラのように。私はヘビーメタルを好んでおり、大きな音を鳴らしたいと思っている」
〈原形〉好意的に受け入れられたプレッシングスタイル(15/16シーズン)
プレミアリーグ:8位
FAカップ:4回戦敗退
カラバオカップ:準優勝
後にレスター・シティでも成功したブレンダン・ロジャースの後を継いだクロップは、2015年の10月にリバプールの監督に就任する。どちらかというと穏やかなフットボールを好み、ポゼッションベースのスタイルをチームに浸透させる監督だったロジャースと比べ、鋭いトランジションを武器にするクロップのスタイルは熱狂的なリバプールのファンにも好意的に受け入れられた。
デビューシーズンのリバプールは、前任者ロジャースのチームと比べて「積極的に守備をする意識を持つチーム」として復活した。デビュー戦の相手となったのは、マウリシオ・ポチェッティーノが率いるトッテナム。クロップのゲーゲンプレッシングと比べるとプレッシングを仕掛けるエリアは低いが、密度を高めた中盤の強烈なプレッシングを武器にしたチームだ。
既にサウサンプトンでも中盤の整備に成功し、プレミアリーグでも実力を証明していたポチェッティーノのチームに、初戦からリバプールは激しく「ボール狩り」を仕掛ける。当然ながら監督としての準備期間が短い中で、クロップがチームに意識させたのはプレッシングのトリガーだった。
ロジャース時代はボールの奪い方が不明瞭になっていたチームに、クロップは「相手が後ろを向いて受けたら、複数枚でのプレッシングを仕掛ける」というシンプルなプレー原則を与えた。まだまだ未熟ではあったが、その意識の変化はチームのポテンシャルを開花させようとしていた。
統計データもその変化を如実に表しており、守備のデュエル数が飛躍的に増加した。守備のデュエル数は、デビューシーズンとなったプレミアリーグの終了時に3番目に多かった。
リーグの順位は8位でシーズンを終えた彼らはサウサンプトンやウェストハムよりも順位が下だったが、クロップの影響力は明らかだった。リバプールはボールをロストした後に迅速にプレッシングを仕掛け、相手のカウンターを妨害しながらショートカウンターを狙う。どちらかというと創意工夫しながらフォーメーションを変えていったロジャースと比べると、クロップは組織とスタメンを大きく弄らなかった。ベースになったのは4バックで、4-3-2-1と4-2-3-1が多かった。
そしてシーズンが進んでいく中で、クロップは幾つかのプレッシングにおけるルールを仕込んでいく。最も頻繁に使われたのは、サイドに追い込んだ相手に唯一「インサイド」のパスコースを与え、その選手が外側を向いてボールを受けた瞬間に複数枚でプレッシングを狙うというトラップだった。
この状況では相手選手は限定された視野でプレーすることになり、ボールの近くにいたサイドアタッカーから猛烈なプレッシャーを受けることになる。そのようにサイドでボールを奪うメカニズムに合わせ、リバプールの攻撃はハーフスペースやサイドからの攻撃を好むようになる。ルーカス・レイヴァやエムレ・ジャンが守備的な中盤でプレーすることが多く、攻撃的なポジションはアダム・ララーナやジェイムズ・ミルナー、ロベルト・フィルミーノやフィリペ・コウチーニョが併用されていた。
プレッシングの判断が良い選手が少しずつ重用されるようになっており、ジョー・アレンやジョーダン・ヘンダーソンがシーズン後半には出番を増やしていった。特にアレンは献身的に走り回り「ウェールズのシャビ」という異名には似合わない泥臭いプレーでパスコースを消しながら、チームに貢献していた。また、フィルミーノやララーナも賢いポジショニングでプレッシングを牽引しており、クロップのチームで中核を担うようになっていった。
ロジャース時代からチームの中心だったダニエル・スタリッジやコウチーニョは創造性で攻撃にアクセントを加える存在だったが、強度の面では課題も抱えていた。特にスタリッジは怪我も多く、稼働率も低かった。ピッチに立てば違いを作れるストライカーではあったが、それでも前線の補強は急務だった。
2016年の夏、クロップはチームが最も欲していた選手の獲得に成功する。
クロップのフットボールにおいて、理想となるアタッカーだったサディオ・マネだ。レッドブル・ザルツブルクのSDをしていたラルフ・ラングニックが発掘した才能は、ロジャー・シュミットの指導で飛躍的に成長する。ラングニックとシュミット、クロップと同胞の「ゲーゲンプレッシングの担い手」によって鍛えられたマネは、リバプールというチームに就任したばかりのクロップにとっては「チームの手本」としても獲得しなければならない選手だった。
そしてマネはクロップが抜擢した中でも、ハイプレスのチームに最も適合する選手の1人だった。スピードとパワーを兼ね備えたセネガル代表は、圧倒的なスタミナで上下動を繰り返す。そこまで身長が高い訳ではないがフィジカルが強く、低い重心でボールを力強く運んでいく。
推進力は彼の武器で、特にドリブルでは相手がボールを奪っても「クリーンに奪える場面が少ない」ことからチームが「即時奪回を狙うプレッシング」に移行しやすい。キープ力があってフィジカルも強いことから、なかなか相手も綺麗にボールが奪えないのだ。
華麗なフェイントを仕掛けて相手を抜くことがあっても、一方で簡単にボールを奪われてカウンターを浴びるようなプレーの波がある選手は、クロップのチームで輝くのは難しい。一方でマネは粘り強いキープでチームを助け、ロングボールの受け手としても機能する。身長が高い訳ではないが跳躍力もあり、ヘディングでも簡単には競り負けない。相手のサイドバックに競り勝てば、そこから一気にショートカウンターが炸裂する。
守備の技術にも優れ、タックルの成功率は守備的なMFに匹敵することもあり、自らボールを取り返すプレーも多い。このゲーゲンプレッシングの申し子を獲得したことは、クロップのチームにとっては最大の補強だった。
もう1人、チームの軸になる補強がジョルジニオ・ワイナルドゥムだった。このオランダ人MFは派手なタイプではないが上下動を繰り返すスタミナで知られ、エリア内に入ってのヘディングも得意としている。タフな守備をこなしながら攻撃ではアタッカーをサポートする彼は、中盤であれば様々なポジションに対応する万能MFだった。
元々はサイドアタッカーとしてその能力を認められていた彼だが、プロとしてプレーする中で主戦場を徐々に中央に移していった。現有戦力にはない馬力、そしてエリア内で仕事が可能なフィジカルを兼ね備える選手を獲得することで、センターフォワードの不足を補おうという狙いもあったはずだ。
売却のオペレーションも着実に進め、ロジャースにとっての悪夢になってしまったセンターフォワードのクリスティアン・ベンテケをクリスタル・パレスに放出。彼は若くテクニックもある長身のフォワードだったが、ハイプレスのチームに適応するタイプではなかった。若いジョーダン・アイブとそれなりに出番を得ていたジョー・アレンも売却したが、その2人の穴は新戦力で埋まると考えていたのだろう。
ベンテケの放出は、クロップのスタイルが「純粋なターゲットマン」にそこまで依存しないようになっていることを象徴していた。クロップのフットボールでは上下のランを繰り返すことが求められ、機動力よりもフィジカルで勝負するタイプは好まれなかった。これはクロップの在籍中、傾向として続く部分だった。
〈骨格〉コンバートと補強。見えてきた理想の形(16/17シーズン)
FAカップ:4回戦敗退
カラバオカップ:ベスト4
チームを確実に改善してきたクロップは、チームのフォーメーションを4-3-3に変更した。4-2-3-1よりも両サイドが高いポジションを保つことで、積極的な前線からのプレッシングで相手サイドバックの自由を封じるだけでなく、カウンターで走れる枚数も多くなる。
チームを前傾姿勢にする上で、長い距離を戻ってくることを厭わないマネとワイナルドゥムが中軸になっていく。変わらずに主軸として活躍したのがフィルミーノやコウチーニョ、ララーナだ。特にララーナは安定したプレーで、チームで最も信頼すべき選手の1人となった。
DFライン、特にサイドバックのポジションでは攻撃的なポジションで裏のスペースを手放すことも少なくなかったアルベルト・モレノの出番が減り、MFだったミルナーがコンバートされることになる。守備力やスピードでは厳しい部分もあったが、クロップは彼のスタミナとゲームを理解する能力を評価していた。
そしてミルナーを主力としてチームに残したことで、クロップはプロフェッショナリズムを理解するチームを築いた。献身的な姿勢で知られた彼は、慣れないポジションでも懸命にプレーすることで多くのチームメイトにポジティブな影響を与えたのだ。
加えて、イングランド人としてチームの心臓となったのがヘンダーソンだった。献身的で器用なプレイヤーとして知られていたMFはクロップのチームに定着し、徐々にリーダーとして覚醒していった。
リバプールは中盤を支配する回数が増え、攻撃陣も躍動した。フィルミーノがセンターフォワードに定着したのも、このシーズンだった。華麗な技術を誇るテクニシャンでありながら、献身的なプレッシングを欠かさない彼はモダンなセンターフォワードとしての新しいプレースタイルを確立していく。
クロップにとってプレミアリーグで初めてのフルシーズン、リバプールは首位を争いながらも失速。4位でCL出場権を獲得したチームは78得点、42失点という数字を残した。4-3-3のフォーメーションで得点能力を伸ばした彼らだったが、失点の多さが悩みだった。彼らは引いたチームに苦戦し、カウンターから崩されてしまうことも少なくなかった。
とはいえ、このシーズンの功績はクロップのリバプールにおける代名詞となる「破壊力抜群の3トップ」というシステムを確立したことだろう。フィルミーノ、マネ、コウチーニョの3トップはいずれもプレミアリーグで2桁得点を叩き出し、攻撃的なチームを牽引した。ポジションに固執することなく流動していく3トップは相手チームを悩ませ、全員がフィニッシャーになれる柔軟性を誇っていた。
〈猛威〉攻守の要の加入と完成した左サイド(17/18シーズン)
プレミアリーグ:4位
FAカップ:4回戦敗退
カラバオカップ:3回戦敗退
16/17シーズンの準備期間に度重なる遅刻でクロップを怒らせてしまったママドゥ・サコーを完全移籍で放出。クリスタル・パレスにレンタルされていたセンターバックを、そのまま2820万ユーロ(約39億円)で完全移籍させたことで補強資金を確保した。また、長くチームに所属していたルーカス・レイヴァもこのタイミングでセリエAのラツィオに移籍している。バランス感覚に優れた選手ではあったが、リバプールは中盤の若返りも進めていく必要があったのだ。
余剰戦力を売却した移籍市場でメインの補強となったのが、4200万ユーロ(約59億円)で獲得したモハメド・サラーだ。ASローマでその攻撃力を開花させた右サイドのアタッカーは、クロップにとっては「カウンターの担い手」となる選手だった。ドリブルだけでなくオフ・ザ・ボールでも快速でディフェンスラインの裏を攻略するエジプト代表のエースは、クロップによってプレミアリーグに復帰する。
若手時代にスイスのバーゼルでプレーした彼は、チェルシーで挫折を味わっていた。当時からスピードを武器にしていたが、どうしても狭いスペースに誘導されてしまう癖があり、プレーの幅が狭いことが弱みだった。縦に全速力で突破しても、その後に効果的なプレーを選択できていなかったのだ。
そんな彼を成長させたのが、イタリア・セリエAだ。スペースを閉鎖することに長けたディフェンダーとの対戦を重ねることで、オフ・ザ・ボールのランニングが磨かれたのだ。サイドライン際を縦に突破するプレーだけでなく、中央のスペースを使えるようになったことでサラーは危険なアタッカーに変貌した。
そしてリバプールに加入してからも成長を続けた彼は、抜群のシュート技術でゴールを量産するエースとなった。シュートパターンも多く、ゴール前で決定的な仕事をこなす彼によってリバプールの攻撃力は倍増した。
もう1人、後に絶対的なレギュラーになったのがアンドリュー・ロバートソンだ。ハル・シティでも気の利いたプレーでチームを支えていた仕事人は、リバプールでダイナミックな長距離のランを武器に攻守に活躍。サイドのレーンをたった1人で制圧する彼の存在によって、リバプールはサイドからの攻撃をパワーアップさせた。
900万ユーロ(約13億円)の移籍金は格安で、チームにとっても賢明なビジネスになった。敵陣の深いポジションまで侵入する圧倒的なオーバーラップを繰り返す彼は、サディオ・マネと連携しながら左サイドを切り崩すようになっていく。ハル・シティ時代から能力の高さは評価されていたが、ここまでリバプールのプレースタイルにピッタリと適合したのは幸運だった。
マネとロバートソンの連携によって、リバプールの左サイドは攻守両面で隙のないエリアとなった。また、クロップは彼のドリブル能力を使って相手のハイプレスを回避するような戦術パターンも使っていた。ロバートソンがインサイドにドリブルをしながら侵入して相手の守備を誘い出し、相手の守備組織を崩すパターンは興味深いものだった。
新戦力が躍動したリバプールは、昨年までのチームを大きく底上げすることに成功する。ゲーゲンプレッシングからのカウンターは鋭く、サラーは開幕からゴールを量産してプレミアリーグで32ゴール。得点王に輝いた彼がチームを爆発させることで、リバプールの歴史に残る3トップが完成する。
フィルミーノは創造性と献身性を兼ね備えながらハイプレスのスイッチとなるだけでなく、そのブラジル人らしいトリッキーなプレーで両WGをサポート。そこから両WGがゴールを狙うシステムは、これまでのリバプールでも中心選手だったコウチーニョへの依存からの脱却を可能にする。
パンチ力があるミドルシュートと創造性を武器にしたブラジル人アタッカーを1億4000万ユーロ(約196億円)で冬にバルセロナに売却したことは、リバプールにとって理想的なビジネスだった。一方でバルセロナ移籍後、コウチーニョはそれまでの輝きを失ってしまい、怪我に苦しむことになる。
創造性のある選手よりもタフな快速アタッカーを重視したのは、クロップらしい決断だった。同じブラジル人でも、クロップはプレーにムラが少なく、戦術的に幅広い仕事を担えるフィルミーノを重用していた。「ゲーゲンプレッシングこそが、最高のゲームメイカーだ」というのはクロップの言葉だが、彼らは1人のゲームメイカーに頼るゲームモデルではなく、激しいプレッシングで相手からボールを奪うことで直線的なショートカウンターを狙うというアプローチに少しずつシフトしていた。
これこそが自らも司令塔として知られ、自分のチームでも多くの司令塔を重用してきたペップ・グアルディオラとの最大の違いだろう。グアルディオラのチームにはセルヒオ・ブスケツやロドリがおり、チームの意思をコントロールする役割を担ってきた。
彼らの柔軟性と戦術眼は攻撃のバリエーションを支えたが、一方で彼らがいないチームは脆くなってしまい、ブスケツの穴を埋めるというのは不可能なタスクになってしまった。同時に現在のマンチェスター・シティであっても、ロドリがいないと一気にチームとしての一体感を欠いてしまう。23/24シーズンにおいても、グアルディオラのチームが最も苦しんだのは「ロドリ不在時」だった。個に依存してしまうチームではなく、クロップはプレッシングというチーム戦術を最大限に活かすことで負荷を分散する手法を好んできた。
そして冬には、サウサンプトンからフィルジル・ファン・ダイクを獲得する。セルティックからサウサンプトンに移籍し、プレミアリーグ屈指のCBとして評価を高めていたファン・ダイクに、リバプールは8400万ユーロ(約118億円)の移籍金を投じた。当時のプレミアリーグ最高額だったが、ここでトップクラスの選手を躊躇することなく補強したのが「リバプールの補強部門」の慧眼を示していた。彼らはデータ分析とチームのゲームモデルを考慮し、ハイラインを維持するためにファン・ダイクが必要だと確信していた。
ファン・ダイクの獲得によって、リバプールというチームは完成する。空中戦では無敗に近い強さを誇り、スピードでも対面するアタッカーを容赦なく封じる彼によって、チームは今まで以上にゲーゲンプレッシングを迷わずに仕掛けられるようになった。ファン・ダイクは足下の技術も安定しており、ビルドアップでチームが安易にボールを失うことを避けられる選手だった。
右サイドでは長年プレーしていたナサニエル・クラインに代わり、ジョー・ゴメスとトレント・アレクサンダー=アーノルドが出場機会を争うようになる。アーノルドは独特のテクニックとキック精度を誇り、一発のパスやフリーキックでチームの状況を一変させる選手として成長していく。
プレミアリーグは4位で終わり、2年連続となるチャンピオンズリーグへの出場を決める。チャンピオンズリーグではマンチェスター・シティを破り、ローマとの準決勝でも勝利。決勝戦ではレアル・マドリードに1-3で敗戦したが、クロップのチームは欧州の頂点に近づいた。決勝戦ではプレッシャーに苦しめられたロリス・カリウスが致命的なミスをしてしまったが、それこそがリバプールにとって補強すべきポイントを明確に示していた。
クロップのフットボールは戦術面でも高く評価され、ヨーロッパの識者たちが注目するチームになっていった。17/18シーズンのチャンピオンズリーグを分析したUEFAのテクニカルレポートにおいて、クロップは「新たなる戦術的な潮流の担い手」として紹介された。ポゼッションをベースとしたフットボールの天敵となったクロップのチームは、欧州最高の舞台で破竹の勢いで勝ち進んだ。
それに加えて、ディ・フランチェスコ率いるローマも激しいプレッシングと得点力を誇るチームとして評価されており、準決勝での彼らの激突はノーガードの殴り合いになった。「総得点の51%がファイナルサードでのボール奪取を起点としており、敵陣でのボール奪回が得点に直結する傾向にあった」というデータを証明するような結果を残した両チームは、敵陣でボールを奪えば直線的にゴールに迫っていく。だからこそ彼らは両ウイングを中央に近いポジションでプレーさせており、エバートンやマンチェスター・ユナイテッドを指揮したデイビッド・モイーズは「リバプールの3トップの両翼は極端に中央に絞っており、広くピッチを使うためにサイドライン際に位置する従来のウイングとは役割が異なっている」とコメントした。
アンフィールドでの1stレグはリバプールがゲームを支配し、70分までに5ゴールを決めて「ゲームを終わらせた」かと思われた。しかし最後の10分で2点を返したローマが、2ndレグに希望を残す。2ndレグでもリバプールが2-1とリードしたが、後半にローマが猛烈に反撃する。後半で3ゴールを決めたローマはリバプールを追い詰め、2試合で13ゴールという乱打戦になった。
大事な試合こそ、慎重に守備から……というチームが多かったこれまでのチームと比較すると、その2チームはネジが外れていた。ジョゼ・モウリーニョの守備的なフットボールもグアルディオラのポゼッションも、あくまでチームのバランスを整えることを重視していた。グアルディオラはボールを持つことで安定した陣形を整え、そこからのプレッシングで即時奪回を仕掛ける。しかし、ローマやリバプールは不安定な状況を苦にせず、むしろ不安定な局面に力づくで相手を引きずり込んでしまう。そうなれば、セカンドボールをどちらが拾うかのギャンブルだ。
生に固執するのではなく、死に向き合うような勇敢なアプローチで彼らは一つの時代を築いた。そして、このタイミングで「フィナンシャル・タイムズ」のコラムニストとしても活躍する英国人サイモン・クーパーが「ストーミング」という言葉でリバプールの戦術を表現したことにも言及すべきだろう。
ボールを失うことを恐れる相手を嘲笑うように、クロップのチームは五分五分のボールで相手をカオスな状況に誘い込み、そこからの反射的なプレッシングでボールを奪う。まるで獣の群れのようなプレッシングは、間違いなくヨーロッパの覇権に手を伸ばしていた。
唯一の問題としては、コーチングスタッフのゼリコ・ブバチがローマとのチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグの直前に「個人的な理由」でチームから離脱し、クラブから去っていたことだろう。クロップの右腕として彼を支えてきたアシスタントコーチは、結果的に2019年に正式にチームを去ることになる。そして後釜には、ペピン・ラインダースが呼び戻されることになる。
〈到達〉プレッシングスタイルを高次元へ導く2人(18/19シーズン)
プレミアリーグ:2位
FAカップ:3回戦敗退
カラバオカップ:3回戦敗退
CL決勝まで勝ち進んだチームの勢いを失いたくなかったリバプールは、即戦力の補強に資金を費やす。特に守護神のポジションこそ、チームの弱点になっていた。プレッシャーによって全てを失ってしまったカリウスや、プレーに波があるシモン・ミニョレでは厳しいと考えていたリバプールの上層部は、ASローマからアリソンを獲得する。
ブラジル人ゴールキーパーは欧州トップクラスの実力を誇り、前述したようにハイプレスの撃ち合いを好んでいたローマのスタイルに慣れていた。ハイラインの裏をカバーするスピードとカバーエリアの広さでスイーパー的にプレーすることが可能な現代的なキーパーであるだけでなく、彼はセービングのレベルでも別格だった。
17/18シーズンのローマでのパフォーマンスを分析したデータアナリストは彼の実力に驚かされ、「相手チームのゴール期待値を20%減少させる」とコメントしていた。プレミアリーグという舞台でもパフォーマンスは低下せず、変わらずに世界トップクラスのゴールキーパーとして安定したプレーを披露。メンタル面でも強く「プレッシャーがある局面でも、最もシンプルなプレーを正確に選択する」と評価された。
また、足下の技術もビルドアップとカウンターでチームを支えることになる。ゴールキーパーからのボール配球をディストリビューションと呼ぶが、アリソンはキャッチ後のスローやパントキックでも迅速にチームをカウンターに移行させる事に成功する「ディストリビューションの名手」として知られた。足下の技術もフィールドプレイヤーに匹敵するアリソンはボールを受けても簡単には失わず、プレッシングを得意とするチームにも捕まらない。ファン・ダイクとアリソンによってチームのビルドアップは安定し、「相手のビルドアップを封じながら、自分たちはプレッシングに捕まらないチーム」に変貌しつつあった。
そして、もう1人チームを新しいレベルに導く補強になったのがファビーニョだ。24歳のMFはアンカーのポジションに適合するフィジカルと守備の判断力を兼ね備えており、マンツーマンとゾーンディフェンスの両方に対応できる選手だった。
特にリバプールというチームはプレッシングを主戦術にしているので、ゾーンを守る守備から迅速に「人を捕まえる」マンマークに移行しなければならない。そういった意味では通常の「ゾーンを守る」タイプのバランス感覚を重視したアンカーよりも、対人プレーでも力を発揮する選手を求めていた。そういった意味ではファビーニョは年齢を含め、チームにとって最適な選手だった。
ただ、予想ほどにチームに馴染めなかったのがナビ・ケイタだった。高い移籍金を払って獲得したMFはボールを持ち運ぶスキルと推進力を兼ね備えており、スピーディーなゲームに慣れていた。サディオ・マネと同じくレッドブルグループからの獲得は成功を期待させたが、なかなかリバプールの求める水準には達しなかった。彼が成功していれば、ボール運びにおけるマネへの負担は軽減されていたかもしれない。
シーズンでは4バックが完成形に近づき、右サイドバックには若いアーノルドが主力に定着した。アンドレア・ピルロのように状況を一瞬で打開するキックと視野を持つ男は、自陣から局面を打開するだけでなくアーリークロスで攻撃をサポートするプレーを得意としていた。
センターバックはファン・ダイクとジョエル・マティプがメインとなり、左サイドバックは変わらずロバートソンが上下動を繰り返した。この両サイドバックは攻撃面での違いを作り、3トップでの攻撃が停滞したタイミングをオーバーラップでサポートした。中盤ではファビーニョがレギュラーとして活躍し、これまで以上に堅実なセンターラインが完成する。
アリソンーファン・ダイクーファビーニョによって構成される中央のラインは、相手の攻撃を淡々と跳ね返していく。前線ではフィルミーノがクロップのチームで着実に成長し、そのカバーシャドウで守備面で欠かせないセンターフォワードに成長。フィルミーノが前線から相手のアンカーへのパスコースを封じる位置に立つことで、リバプールのプレッシングは全てが彼からスタートするという意味で、重要な存在だった。変わらずサラーとマネはフィルミーノとともに最強3トップを形成しており、破壊的な攻撃力はプレミア随一になっていた。それを証明するように、このシーズンは充実していた。
唯一の悩みはトランジションを主軸に置くことによる、怪我人の増加と終盤の失速だろう。プレミアリーグでは1ポイント差という紙一重で、マンチェスター・シティに優勝されてしまう。勝ち点97でリーグ優勝を逃すというのは、プレミアリーグの上位チームが桁違いのレベルに達していることを示唆していた。
フットボールの戦術に「完璧」の二文字は存在しない。ストーミングを主軸に置くチームが直面する大きな課題が、選手への負荷増大だ。トランジションを連発するようなスタイルに求められる運動量は多く、フィジカルコンタクトの回数も増加。フィジカルに優れた選手を多くそろえても、どうしてもシーズン終盤の失速は避けられない。
このシーズンになるとリバプールの攻撃力はプレミアリーグでも相手チームが警戒しなければならないレベルになっており、格下のチームはリトリートすることでアタッカーのスペースを無くそうとすることも多かった。その状況で両サイドバックが躍動し、攻撃のパターンを増やしたこともポイントだったはずだ。
プレミアリーグでも最後まで首位を争いながらギリギリでマンチェスター・シティに優勝されてしまったが、チャンピオンズリーグでは偉業を成し遂げる。特にバルセロナを相手にした逆転劇は、CLの歴史に残るゲームだった。
さらにもう1つ、相手が徹底的にリトリートしてくると、トランジションの隙を発見するのは容易ではなくなる。あくまでストーミングは格上を倒すことを目的にリソースを集中する「電撃戦」的なアプローチであり、警戒されてしまうと威力は半減する。バルセロナ相手に披露した完璧な逆転劇も、マネへのロングボールを起点にストーミングを仕掛けたことによって成し遂げられた。
バルセロナとの乱打戦はCL史上に残るゲームだったが、バルセロナ側に油断があったのも確かだろう。左サイドを押し込むことが可能なマネを抑えることを考えれば、本職CBの選手を右サイドに配置するような手段もあったはずだ。3点のリードを意識しながら漫然と試合に入ってしまったことで、バルセロナはリバプールの激しいリズムに飲み込まれてしまった。
〈完成〉リバプールがたどり着いた最高到達点(19/20シーズン)
プレミアリーグ:優勝
FAカップ:ベスト16
カラバオカップ:ベスト8
CL制覇を成し遂げたリバプールの主軸は年齢的にも「最盛期」を迎えており、補強については大規模な動きを必要としていなかった。即戦力ではなく、将来性のある若手とバックアッパーとしてチームを支えるベテランこそ、彼らが狙った補強だった。
センターバックのセップ・ファン・デン・ベルフはこのタイミングでは17歳で、クィービーン・ケレハーも20歳。このタイミングでリバプールU-21チームに加入したケレハーは成長を遂げ、23/24シーズンにはアリソンの負傷時にも見事なパフォーマンスを披露した。また、ウェストハムからフリー移籍で獲得したアドリアンもプレミアリーグを知り尽くした実力者だった。球際に強い彼をアリソンの控えに置けたことは大きく、チームにとっても貴重なベテランとなった。
充実したチームは変わらず強烈なプレッシングと、抜群の破壊力でプレミアリーグを制圧していく。特にファビーニョの守備面における貢献は大きく、プレミアリーグ最高の守備的MFとしての評価を確立した。
両サイドバックが攻撃参加する回数は増え、それに伴いヘンダーソンやワイナルドゥムがサイドバックのポジションに下がり、彼らを押し上げるようなアプローチが増えた。ファビーニョが成長したことで中央を一人で対応する場面が増え、その結果としてヘンダーソンはサイドに近いポジションで仕事をする場面が多くなっていく。
ヘンダーソンは守備面でもスペースを埋めるのではなく、相手のパスコースを消しながらプレッシングをサポートする技術に長けており、サイドでボールを失ったタイミングでは防波堤として機能した。両サイドバックが攻め上がったスペースを、静かに埋める彼のプレーはチームのバランスを保っていた。中盤の選手たちが規律を守り、チームの基礎を支えるために守備で働くことで、アーノルドとロバートソンの両サイドバックは攻撃力を迷うことなく発揮し、それによって多くのチームは守備の局面で苦しめられることになる。
両ワイドのアタッカーが中央に積極的に侵入すると、サイドバックがアーリークロスを積極的に狙っていくスタイルは、多くのゴールチャンスを創出した。アーノルドは特に精度の高いアーリークロスを武器に、攻撃的なチームにおける「陰の司令塔」として活躍していた。
そして、このシーズンにおけるリバプールの戦術的な特徴として「ロングボールの活用」がある。アリソンやDFラインからロングボールを狙うことで一気に状況を打開するだけでなく、リバプールはサイドチェンジも効果的に使っていた。ロングボール戦術の先駆者としても知られるサム・アラダイスは、次のようにリバプールの戦術を解説している。
「リバプールは右サイドから左サイドへ、迅速なロングボールで効果的な攻撃を仕掛けるチームだ。しかし、誰もリバプールがロングボールのチームだとは考えていない。それが前線へのフィードではなく、サイドチェンジだからだ。リバプールがロングボールをシンプルに前線に当てるようなことは少ないかもしれないが、彼らはロングボールを活用している。彼らは、ロングボールをプレミアリーグで最も効果的に使っているチームだ」
この長いボールの活用は、アーノルドというキック力と精度を兼ね備えたサイドバックによって可能になった。しかし、バルセロナとのゲームにおける成功も1つの要因だったかもしれない。マネへのロングボールはチームにとって信頼すべきオプションとなっており、彼に長いボールを蹴ることでチャンスが生まれることもチームの共通認識となっていた。
また、ファウルの少なさも特筆すべき部分だった。当時のマンチェスター・シティがテクニカルファウルと呼ばれるような「流れを止めるようなファウル」を効率的に使っていた一方で、このシーズンのリバプールはターンオーバーをクリーンに奪うことでも注目されたチームだった。
冬には日本代表の南野拓実を補強しており、彼もレッドブルグループからの獲得だった。スピーディーな攻撃にアクセントを加えられる選手として知られており、3トップのバックアップとして複数のポジションに対応する柔軟性も評価されていた。チームには定着しきれなかったが、リバプールとしても3トップに過度に依存することに危険性については理解していたのだろう。本来は供給役としても機能する南野は、前線のオールラウンダーとしてチームに定着する可能性はあったはずだ。
ヘッドコーチのラインダースはチームが連携して「コンパクトな距離感を保つことの重要性」を強調しており、タイミングこそが鍵になると述べた。タックルが遅くなればファウルになる可能性が高まってしまうので、チームの組織的な守備能力を高めることで、正確なタイミングでボールを奪うことが可能になるという理屈だ。
距離感と組織的な守備を整え、彼らは先行して動き出しながら正確なタイミングでボール奪取を狙うことに成功していた。ラインダースが副官となったリバプールは、少しずつポゼッション局面にも重心を置くチームとなってきていた。クロップとリバプールは補強によってチームを完成させ、ゲーゲンプレッシングという流行における一つの最終地点に辿り着くことに成功した。
〈移行〉最強チームを襲った悲劇(20/21シーズン)
プレミアリーグ:3位
FAカップ:4回戦敗退
カラバオカップ:ベスト16
CLとプレミアリーグを制覇したリバプールは、恐らくチーム内で影響力を強めたラインダースの知見を借りつつ、ポゼッション型のチームにシフトしようとした。その目玉となったのが、バイエルン・ミュンヘンから獲得したチアゴ・アルカンタラだ。
希代のゲームメイカーであり、現代フットボールでは珍しい柔らかなターン技術と華麗なフェイクで相手を欺く彼の獲得で、リバプールはビルドアップ局面からチャンスを作りやすいチームへと姿を変えるというミッションに挑むことになる。トップクラスのチャンスクリエイターを補強することで、チームは新しいスタイルへの進化を遂げようとしていた。
また、このタイミングで補強されたのがディオゴ・ジョタだ。前線で複数のポジションをこなせるアタッカーは万能型であるだけでなく、ポジショニングの良さとゴール前の勝負強さを誇る選手だった。彼の獲得はクラブにとって大きく、リバプールは遂に3トップの代役となれるクオリティの選手を手に入れることになった。
しかし、進化を期待されたシーズンは怪我に泣かされることになる。ファン・ダイク、ジョー・ゴメス、マティプをシーズンの大半で欠くことになってしまったDFラインは人員の不足に陥り、中盤の選手がDFラインをカバーしなければならないという緊急事態に陥ってしまった。ファビーニョやヘンダーソンを守備ラインに下げなければならない試合もあり、かなり辛い台所事情でのゲームが続く。
2021年2月のマンチェスター・シティ戦では、まさかのファビーニョとヘンダーソンの2枚をセンターバックに並べなければならず、4失点。冬にはシャルケからレンタルでオザン・カバクを獲得し、若いセンターバックをプレーさせなければならないほどに、センターバックの人材不足には苦しめられた。
守備陣の不足だけでなく、攻撃も期待には応えられなかった。実際にゴール期待値では悪くないゲームでもゴールが入らずに苦しむ場面も多く、チーム全体が機能不全に陥っていた。ファン・ダイクやマティプの不在はチームのビルドアップにも悪影響を与えており、チームが苦しむのは必然だった。DFラインの選手層という面でも、課題を残すシーズンになった。
ポジティブなポイントは、初年度からチームに馴染んだジョタだろう。プレミアリーグ19試合で9ゴールは予想以上の活躍であり、フィルミーノのスタメンを脅かすような活躍だった。一方で29歳のチアゴはチームの不調もあり、なかなかその実力を発揮しきれない場面も目立った。幾つかのプレーで才能を感じさせたが、本人も最初のシーズンを「物足りなかった」と認めている。
また、シーズン終了後にはチームを支えてきたワイナルドゥムが契約満了に伴い退団。これによって、前線で空中戦をサポートする選手を1人欠くことになってしまった。彼の「中盤から前線に走り込み、ヘディングでクロスボールの的になる」という特性は、結局23/24シーズンも「代替できていない」。
〈集大成〉甘い蜜に誘われたリバプールが失ったもの(21/22シーズン)
プレミアリーグ:2位
FAカップ:優勝
カラバオカップ:優勝
リバプールは守備陣のテコ入れとして、センターバックにイブラヒマ・コナテを獲得。レッドブルグループからの補強となり、その圧倒的な身体能力を評価されたDFを獲得することで、ハイラインの背後をカバーすることに成功する。
守備陣の怪我人も戻り、チームとしては改めてリーグ優勝を狙う陣容が整ったシーズンになった。冬にはルイス・ディアスを加え、彼がマネの負担を軽減するアタッカーとして成長していく。その推進力はトップクラスで、大金(5000万ユーロ/約70億円)を払っただけの価値がある選手を補強することに成功した。
前線にディアスとジョタを加え、恐らくクロップ在籍期間でも最も「前線の厚み」を確保できたシーズンになったはずだ。フィルミーノは怪我が少なくなかったが、ハーヴェイ・エリオットも序盤は出番を得るなど、リバプールにとっては将来への投資も含め、充実のシーズンとなった。プレミアリーグでは2位だったが、カップ戦を獲得して「国内2冠」を達成しており、チャンピオンズリーグでも決勝まで勝ち進んだ。
チアゴもチームにフィットし、アーノルドも絶好調となったシーズンは、リバプールが破壊力で他チームを圧倒することも多いシーズンになった。マティプも好調であり、コナテとのポジション争いはチーム内のポジティブな競争を加速させることになった。
このシーズンは、ある意味ではグアルディオラと競い合いながら結果的に両チームが似た能力を習得していった「クロップvsグアルディオラ」の集大成となるシーズンだった。
マンチェスター・シティはリバプールから学び、そのハイプレッシングとトランジション局面での強さを得た。逆にリバプールはチアゴやアーノルドのように創造的なプレイヤーを並べることで、ビルドアップの局面からゴールを狙えるようになった。
右利きのパサーであるチアゴは、右のハーフスペースと右へのロングボールを同時に狙うことで相手の的を絞らせないようなプレーを最も得意としている。いわゆる「偽装するパス」の使い手として、チアゴはこの2パターンのパスを「身体の捻り」で最後まで読ませない技術に長けているのだ。そのチアゴを左サイドに置くことで、リバプールはチャンピオンズリーグの決勝戦でも「ボールを保持しながら崩すチーム」としての力を発揮していた。
しかし、チームとしての集大成であっても、レアル・マドリードを崩すことは難しかった。アンチェロッティはリバプールの圧力に屈せず、確実なビルドアップで少しずつ自分たちの時間を作っていった。そして守備面ではカゼミーロとティボー・クルトワがトップレベルのパフォーマンスを披露して、リバプールの攻撃を妨害した。
そして、このシーズンこそが集大成であり、転機であったように思える。レアル・マドリードが用意していた「非合理性」こそは、リバプールにとって禁断の果実だった。彼らはチアゴとアーノルドがチームに提供する「非合理性」という甘い蜜に誘われるように、少しずつそのアイデンティティーを失っていった。
〈脆弱〉象徴の退団で進むアイデンティティーの喪失(22/23シーズン)
プレミアリーグ:5位
FAカップ:4回戦敗退
カラバオカップ:4回戦敗退
前線の補強を重ねたチームにとって、夏の補強で目玉となったのがダルウィン・ヌニェスだ。リバプールが長年フィルミーノに任せていたセンターフォワードに、フィジカルで戦える大型ストライカーを加えたのだ。
これはグアルディオラのマンチェスター・シティがアーリング・ハーランドを獲得した事実と比較され、プレミアの2強がチームとしての幅を広げようとしていることに注目が集まっていた。冬にはオランダ代表でも活躍したコーディ・ガクポを加えるなど、補強は前線のメンバーに集中した。
しかし、ヌニェスとガクポは序列を覆すことができず、補強としては大成功とは言いづらい。期待外れというほど酷い訳ではないが、チームに欠かせない存在になるには、まだまだ成長が求められる。
このシーズンは少しずつチームのアイデンティティーだった「強度」を失っていたという手痛い指摘もあるシーズンとなった。主軸として陰でチームを支えてきたヘンダーソンやミルナーが少しずつ年齢を重ねており、勤続疲労を抱えていたことで、少しずつチームの強度を失っていた。そこにテクニシャンで、スライディングタックルなどは得意だが予防的なカバーリングなどは苦手とするチアゴを主軸に加えたことで、中盤が少しずつ相手のショートカウンターに脆くなっていたのだ。
更にサディオ・マネもバイエルン・ミュンヘンに放出しており、これもチームとしての質を落とす原因となっていた。他の選手でも推進力やドリブルなど、マネの能力を部分的には補うことは可能だ。だが、ボール奪取とロングボールを収める能力を兼ね備え、ドリブルを仕掛けても徹底して「失うことなくボールを運ぶこと」に強みを持ったマネは、特別な選手だった。
クロップのフットボールを象徴する選手がチームを離れたことで、どうしてもバランスは悪くなる。チアゴが中盤の底でゲームを作ろうとするとネガトラで脆くなってしまい、その結果として「綱渡り」になってしまうような場面が増えた。
そして、偽サイドバックというのも麻薬だった。リバプールはアーノルドの展開力を活かすべく、中央に動かす「偽サイドバック」を導入するが、それもチームのバランスを崩す一因になってしまった。攻撃では魅力的なこの戦術も、中央に移動したアーノルドがカウンターで埋めなければならないスペースが広くなるという課題を抱えており、そこも解決されることはなかった。
クロップとラインダースは変化を求めていたが、グアルディオラという天才があまりにハイスピードで変化に適応していく一方、その変化に振り回されてしまった感が否めない。そしてチームを支えてきた中盤の刷新について、かなり出遅れたのも大きかった。チアゴの創造性という麻薬に手を出してしまったことで、中盤のスペースを埋めていた選手たちの衰えに気づかず、前線ばかりを補強してしまった。
また、怪我から復帰したファン・ダイクのパフォーマンス低下も話題となっている。圧倒的なプレミアNo1センターバックはその加速力を失い、ストライカーに翻弄される場面も少なくなかった。完全に自信を失ってしまい、距離を取りすぎてしまう場面も目立つようになった。
〈刷新〉ラストイヤーの失敗と功績(23/24シーズン)
プレミアリーグ:3位
FAカップ:ベスト8
カラバオカップ:優勝
大刷新のシーズンとなってしまったのは、補強戦略の失敗だろう。ファビーニョとヘンダーソン、フィルミーノといったリバプール黄金期のメンバーが抜けたことで、中盤の枚数を揃えなければならなかった。ソボスライ・ドミニク、アレクシス・マック・アリスター、遠藤航、ライアン・フラーフェンベルフを獲得し、中盤の陣容を一気に入れ替えた。
新たに加わった中盤の選手たちは、実力を備えていた。リバプールのベースとなる運動量と守備貢献を欠かさない性質を持ち、特にソボスライとマック・アリスターの2枚は万能型として、どの局面でもチームを支えられる選手として活躍した。
リバプールが複数のターゲットを逃した後に代役として獲得した遠藤には、守備面で大きな期待を寄せられ、その前評判を覆すようなパフォーマンスでチームに適合した。中盤の底が足りないチームにとっては大きな補強になったのは嬉しい誤算だったが、リバプールが結果的にアンカーとしてファビーニョの後釜となる選手を適切に用意できていなかったことも事実だった。
チアゴは怪我を繰り返し、戦力としては期待できなくなっていたこともあり、チームとして中盤は「試運転をしながら」というシーズンになった。若きカーティス・ジョーンズやエリオットが成長を感じさせたポジティブな要素もあったものの、あまりに計画性のない状態で走っていたのは事実だった。
それでも前線の破壊力は変わらず、守備ではファン・ダイクが復活。見事に守備の要としての自信を取り戻し、それぞれのポジションで若手が台頭した。セカンドゴールキーパーとは思えない落ち着きで後方を支えたケレハーやセンターバックとして活躍したジャレル・クアンサーなど、アカデミー出身の選手たちが実力を発揮した。
そして、絶対的な存在だったアーノルドもコナー・ブラッドリーの成長により、そのポジションを脅かされることになった。特に守備面での不安定なパフォーマンスは改善されておらず、ブラッドリーは守備面ではアーノルドを上回っている。最終的にはチアゴとアーノルドへの依存からチームが少しずつ脱却しつつあり、再び強度を取り戻さなければならないということを実感しているはずだ。
アーセナルとマンチェスター・シティとの三つ巴の優勝争いを盛り上げたリバプールだったが、やはりチームは歪なバランスで成り立っていた。崩しの局面になると若きエリオットの双肩に負荷が集中し、中盤と前線を繋ぐ選手の不在を感じさせた。そして攻撃面でもヌニェスは期待されている仕事をこなせず、直線的にシュートを狙う癖を読まれ、ゴールキーパーやディフェンダーに防がれてしまう場面も多かった。
チームとして攻撃の局面ではトップクラスの破壊力を感じさせたが、ハイプレスの強度ではアーセナルに劣るチームになってしまい、それこそがクロップのラストシーズンという花道を飾れなかった最大の理由だろう。
ミケル・アルテタのチームは若く、激しいプレッシングではマルティン・ウーデゴールがフィルミーノを思い出させるような「賢いパスコースの遮断」で相手の自由を奪い、そこから前線のアタッカーが容赦なくプレッシャーを仕掛けた。そして中盤にはトーマス・パーティーやデクラン・ライスが君臨し、容赦なく相手のボールを奪った。アーセナルとアルテタはグアルディオラではなく、クロップ全盛期のチームを模倣しているようにさえ感じられた。
クロップのラストシーズンはチームの刷新という、最も難しい仕事を行わなければならなかった。しかし、それを完遂することこそが彼の責任だったはずだ。1シーズン前にチームを引き継いだ場合、それは新監督にとって大きなチャレンジになったはずだ。中盤の刷新と若手の抜擢によって、新監督の望むチームを作る礎は整った。
そして、アーノルドやチアゴといった「博打的なカード」についても、その依存度を大きく下げることに成功した。チアゴは今シーズンでリバプールを退団することが決まっただが、アーノルドはチームに残るはずだ。そのアーノルドの代役、競争相手を用意したこともクロップの重要な仕事だった。
クロップという指揮官のキャリアを考えたとき、やはりゲーゲンプレッシングと強度、そして対人マネジメントこそが最大の武器だ。ラインダースと一緒に進化を目指したリバプールだったが、残念ながらその進化には失敗してしまった感が否めない。しかし、一時代を築くだけでなくリバプールを欧州のトップクラブへ蘇らせた彼の功績は大きい。
プレミアリーグを盛り上げてくれた監督が去ることは悲しいことだが、リバプールにとっては恐らくベストの節目だろう。今のチームは悪い状態でも、プレミアリーグの優勝を争えるレベルにある。そのように考えると、このチームのポテンシャルは恐ろしい。ファン・ダイクとアリソンもチームに残るだろうし、まだ数年はクロップのチームを知るメンバーも若手の成長に力を貸すだろう。
【了】