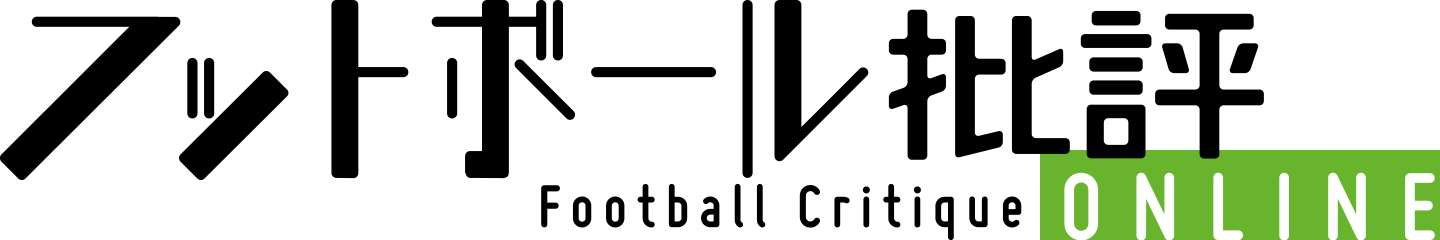W杯で起きた頭突きの結論
――再び代表に話を戻すと、フランスはEURO2000で優勝するも、2002年ワールドカップはグループリーグ敗退。ジダンは1試合しか出場せず、日本の地すら踏むことができませんでした。陣野さんは「地球儀を線で結べたチームの終焉」と表現しています。
「ジダンの関連本でも2002年のことは誰も触れていなくて、2002年はなかったことになっています。98年のチームを引っ張り続けてきたものの、チームとしての役割を終えていたということでしょう」
――少し早送りをすると、ジダンはEURO2004で代表を引退します。その後テュラム、マケレレとともに復帰し、2006年ワールドカップ決勝におけるヘッドバットでピッチを去ります。この間に登場するのが、監督のレイモン・ドメネクで、ドメネクに関して陣野さんは一貫して悪意のある書き方をしています。
「そのように読めるということは、彼のことが嫌いなんでしょう(笑)。話は逸れますが、東大の先生には『はじめにでジダニスト宣言をしている時点でタイトルとの矛盾がある』と指摘されています。その矛盾が特にドメネクの部分に出ているのかも(笑)。ドメネクは行政的な手腕に長けていて、人事異動の機微を掴める会社に一人はいるいやらしいタイプ。だからこそ育成年代を含めて長く協会にいられたのでしょう。ジダンとの関係性もいいはずがなく、戦術、トレーニング方法などでぶつかっています」
――ベテラン3人にドメネクが復帰要請するくらいですから、当時のフランス代表には何かが欠けていた、と。
「ドメネクがチームを作れなかったことに尽きます。特にDFラインが固められず、フィリップ・メクセス、ミカエル・シルヴェストル……う~ん、どうなの? という感じ。ニコラ・アネルカ、ジブリル・シセなどの才能をまとめきれなかった」
――と言いつつ、2006年ワールドカップでは決勝まで上り詰めます。本書は三章に入っていくわけですが、本章はほぼヘッドバッドの話。特に神話学のくだりは、「正直、眠くなりました」とお伝えしたことを思いだします。
「神話学は数えてみたら34ページ。圧倒的に長い。学会誌のアーカイブに『ヘッドバット』と検索すると無数に関連記事が出てくるのですが、引用した文献はもう異常なまでの執念を感じます。ヘッドバットの結論ですか? 何もありません。ただ、生物学の観点から分析した文献があればより面白かったな、と。自分の本でありながら、三章は書き手のコントロールが利いていない(笑)。小説を書いているとき、書いているのは本人なのに、登場人物が何をするのかわからなくなっていく現象に似ています」